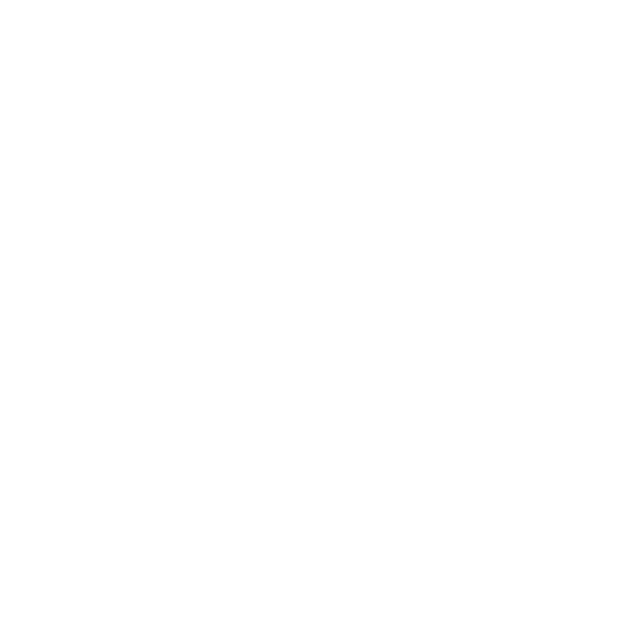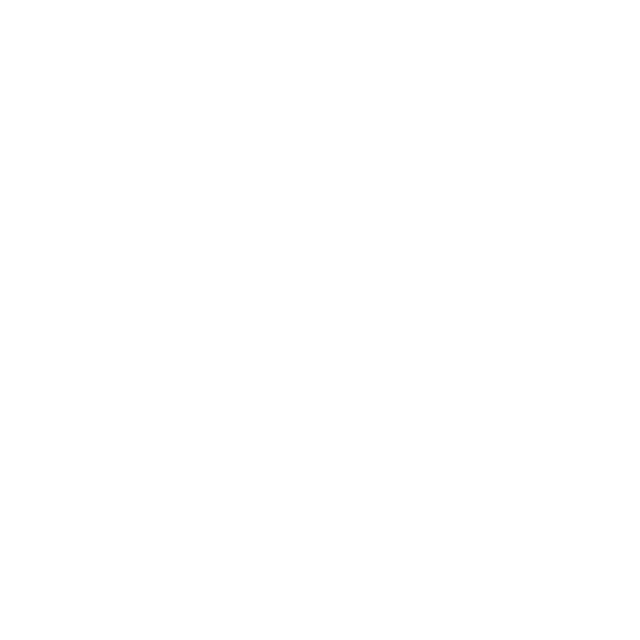境港サーモン
当社の主力商品である「活〆(かつじめ)境港サーモン」こと、
境港サーモンは多くの方々から高い評価を得ています。
ここでは、その生産サイクルや独自の給餌システムを
ご紹介いたします。
境港サーモンとは鳥取県生まれのギンザケ
養殖部境港事業本部では淡水養魚場3ヵ所、採卵センター、海面養殖場の計5拠点を持っています。
大山の周囲に点在する船上山採卵センターと本宮・福原川・清水川の各淡水養魚場にて、採卵・人工授精から稚魚まで育て上げ、その後、美保湾にある海面養殖場のサークル生け簀で養殖します。
日本海の早い潮流、荒海という環境で育ったギンザケは、運動量が多く脂が適度に乗り、身が締まっています。
また三陸より低水温期が短いため、餌の食いつきが良く成長が早いこともあり、三陸では4月下旬から出荷していたのが、約1ヵ月早い3月下旬には出荷できるようになりました。
地元では冬と夏の端境期に水揚げされる養殖サケを新たな名産に期待する向きも多く、こうした地元の期待に応えて、境港の養殖ギンザケを「境港サーモン」と名付けました。
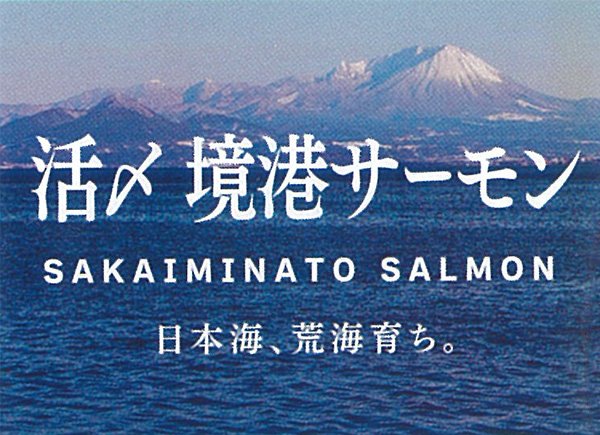


生産サイクル稚魚の育成から販売までを一貫管理

採卵と人工受精(船上山採卵センター)
ー 11月~12月
自社で選抜した優良親魚より採卵します。
精子の活性や卵質も確認して、良質な発眼卵を生産しています。

淡水養殖(本宮、福原川、清水川養殖場)
ー 1月~12月
大山と蒜山の清浄な伏流水を使用し、卵から魚体重200gまで育て、海面養殖場に移動します。
また海に出すまでは何度もサイズ選別を行い、サイズの揃った魚が出せるように努力しています。

海面養殖
ー 12月~5月
日本海に面した美保湾で養殖します。
冬場の日本海は時化が多いので、給餌は自動搬送装置と自動給餌機を組み合わせることで安定して給餌ができ、さらに安全性を高めるとともに省人化にも成功しました。

水揚げ・活〆処理
ー 3月下旬~5月下旬
出荷魚は、沖の養殖場から加工場前の岸壁までイケス曳航し、電気鎮静化台で通電処理した後、1尾ずつ手早く活〆します。また、同時にサイズ選別も行います。

加工
ー 3月下旬~5月下旬
水揚げ魚の生鮮出荷と冷凍原料の生産をします。
ー 6月~3月
冷凍原料から製品(切身・生食用フィレ等)の生産をします。

お届け
ー 高品質の商品をお届け
温度管理を厳しく行うことで、高品質の商品をお届けします。
また、業務提携している運送会社により、数箱から1000箱以上の製品を全国に運ぶことが可能です。
美保湾沖合い生け簀と認証サーモン

本社岸壁から約3km離れた海上に、直径25mのサークル生け簀を22基据え付け(2025年4月現在使用しているのは19基)、各生け簀の中央には自動給餌機を設置しています。
そしてさらに「大規模沖合養殖給餌システム」を採用。プラットフォーム上に最大100t入る飼料貯蔵タンクから、給餌機に配管で飼料補充を自動で行い、安全性の向上と省力化を実現しました。
また特定の生け簀には、ASC認証の基準をすべてクリアした卵・稚魚・飼料のみを使用し、環境に配慮した養殖を行っていることが認められているため、ASC認証のサーモンとして販売することが可能です。
さらにASC生け簀含む全ての生け簀は、養殖認証の4原則をクリアしている(飼料要件・薬品要件等を満たしている)ため、MEL(CoC認証含む)認証のサーモンとして販売することができます。
- ASC認証とは
国際的な水産エコラベル認証で、環境と社会への影響を最小限にした責任ある養殖の水産物であると認める認証制度。 - 養殖認証の4原則とは
社会的責任・対象水産物の健康と福祉・食品安全性の確保・環境保全への配慮の4つ(全116項目)を指す。 - MEL認証とは
日本発の水産エコラベル認証で、水産資源の持続的な利用、環境や生態系の保全・管理へ積極的かつ効果的に取り組んでいる日本の漁業や養殖業の生産者であると認める認証制度。
AI体測と動画カメラによる給餌システムの確立

① AIによる魚体測定と給餌管理
従来は、タモで捕獲したサーモンを麻酔液で眠らせ、魚体測定(以下:体測)として1尾ずつ重さと尾叉長を手作業で計測し、各イケスの平均魚体重を出していました。しかし、正確性や時間・労力、また魚へのダメージを考え、水中用3Dカメラでイケス内の魚を撮影し、AIに魚体を学習させて魚体重を導き出し、数値化させるシステムを導入しました。

その結果、飛躍的に体測のサンプル数が伸び、問題点が解消。さらに得られたAI体測データから成長予測を作り、またその時々の状況(摂餌活性の様子、魚の増重)に合わせ、給餌量を自動で増減または停止できる自動給餌システムのAI化にも進化を遂げました。
「見える化」させることで、管理能力や生産性の向上、また残餌の減少や省力化につながるなど、AIを積極的に活用し養殖のよりレベルの高い世界を目指しています。

②リアルタイム給餌の確立
今までは、給餌機下の水中1.5mに設置している静止画カメラの画像や食欲センサーの情報から、魚の状態を把握し、給餌量の調整を行っていました。しかしそれを動画カメラにすることで、リアルタイムで魚の摂餌活性が簡単に見て取れることが可能になりました。また、今までのシステムは給餌開始と停止を操作するプログラム上、5分~10分のタイムラグが発生していたのですが、新システムに変えたことにより数秒の誤差程度で給餌を操作することが可能となり、給餌のチャンスロスを低減させることに成功しました。
活〆処理 -高鮮度・高品質を保つ秘訣

「境港サーモン」の生食用加工は、夜明け頃に開始され、海上の出荷用生け簀から生きたギンザケを工場敷地内の水揚げ場まで、フィッシュポンプで海水とともにダイレクトに送ります。
電気鎮静化台で気絶させた後、直ちに1尾ずつ活〆し脱血させることで死後硬直を遅らせることができるため、長時間高い鮮度を保つことができます。また、生臭さも低減します。これらは多くの手間とコストがかかる作業ですが、活〆するかしないかによって品質に大きな差が出るため、弓ヶ浜水産では全量活〆処理を行なっています。
また、フィッシュポンプを使うことで、従来の水揚げ方法よりも魚にかかるストレスを減らすことができ、より元気な状態で活〆できるようになりました。
さらにこんな部署もあります!
【 企画・開発課 】
企画・開発課は、日々、魚の健康チェックを行っております。淡水また海洋で何らかの影響で斃死魚が出た場合、検査を行い、病気と判断した際には蔓延しないよう食い止める指示や処置を行います。その他にも、各認証の維持更新に関する業務や、マネジメントシステムのスケジュールに則り、食品安全に関わる従業員教育を養殖部に行うなど、安全で安心な商品を提供できるよう努めております。

① 採卵と育種【完全養殖】
毎年11月中旬から12月中旬にかけて、親魚から採卵・受精させて、次の世代の子どもを作る作業をしています。親魚は、海面に沖出ししたサーモンの中でも大きく育った個体を厳選し交配させています。現在、佐渡サクラマスの全量および、境港・佐渡・岩手大槌サーモンの一部に船上山採卵センターで育った完全養殖の稚魚が使われています。
② 技術開発
鳥取県栽培漁業センターと共同で、より効率よく魚を育てる方法を研究しています。例えば、適正な飼料の組成、馴致沖出し方法の改良、高水温に強い魚を見つける耐性試験実施など、ありとあらゆる可能性を探っています。

生産場所鳥取県境港市 美保湾